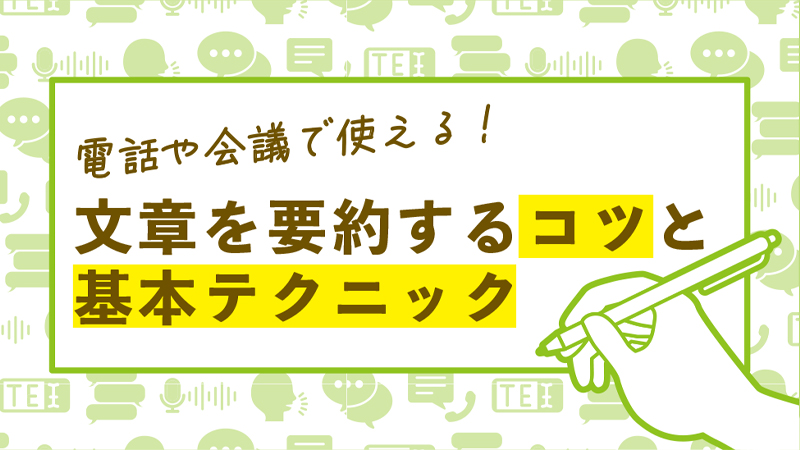宿泊業界の現状と課題 リピーター獲得に向けた改善のヒント

日本の宿泊業界は今、大きな転換期を迎えています。インバウンド需要の回復が期待される一方で、深刻な人手不足や設備の老朽化、デジタル化の遅れなど、解決すべき課題は山積しています。
こうした状況下で経営を安定させるために注目されているのが「リピーター獲得」です。新規顧客の開拓に比べて低コストで集客でき、安定した収益基盤となるリピーターの存在は、宿泊施設の持続的な運営に欠かせません。
本記事では、宿泊業界が直面する現状と課題を整理し、リピーター獲得を軸とした経営改善のヒントを探ります。
慢性的な人手不足が引き起こす運営リスク
宿泊業界における人手不足は、もはや一時的な問題ではありません。サービスの質の低下、既存スタッフの過重労働、そして最悪の場合は営業機会の損失まで、経営全体に深刻な影響を及ぼしています。
特に地方の観光地では、若い働き手の確保が困難を極め、外国人スタッフに頼らざるを得ない状況が続いています。しかし、この解決策にも新たな課題が潜んでいるのです。
地方・観光地で深刻化する人材確保の実態
厚生労働省の調査によると宿泊業界の離職率は26.6%と、全産業平均の15.4%を大幅に上回っています。この数字が示すのは、単なる人材不足ではなく、働く環境そのものに根深い問題があるということです。
長時間労働に見合わない給与水準、土日祝日の勤務が当たり前の勤務体系、体力的にきつい業務内容。これらの要因が重なり、特に若年層の定着率が低い状況が続いています。
地方の観光地では事態はさらに深刻です。都市部への人口流出が続く中、地元での求人に応募する人材自体が減少しています。ある温泉地の旅館経営者は「東京よりも高い時給を提示しても、なかなか応募が来ない」と嘆きます。
2023年の年末年始には、インバウンド需要が回復傾向にあったにもかかわらず、人手不足のために客室稼働率を意図的に下げざるを得ないホテルが相次ぎました。需要があっても供給できない、この矛盾した状況は経営者にとって大きなジレンマとなっています。
外国人スタッフへの依存とシフトの不均衡が生む新たな課題
人手不足の穴を埋めるため、多くの宿泊施設が外国人スタッフの採用を進めています。訪日外国人客への多言語対応という面でもメリットがあり、今や外国人スタッフは宿泊業界に欠かせない存在となりました。
しかし、この流れにも課題があります。日本人スタッフが敬遠しがちな夜勤や早朝勤務を外国人スタッフに頼ることで、特定の人に業務負担が集中する傾向が見られます。
ある都市ホテルの人事担当者は「外国人スタッフは真面目で働き者が多いが、それに甘えてしまっている面もある」と内情を明かします。結果として、シフトの不均衡が生まれ、外国人スタッフの離職につながるケースも少なくありません。
さらに、小規模施設では「一人が休むと代わりがいない」という切実な状況があります。就労条件総合調査によると有給休暇の取得率は全産業平均の半分程度(5.9日)にとどまり、スタッフの疲弊は限界に達しています。
このような無理な勤務体制は、サービスミスやクレームの増加を招き、結果的に顧客満足度の低下につながります。人材確保と働き方改革は、もはや待ったなしの課題といえるでしょう。
デジタル化の波がもたらす効率化と顧客満足の両立
深刻な人手不足に対する有効な解決策として、デジタル技術の活用が注目されています。単なる省力化だけでなく、顧客体験の向上にもつながるデジタル・トランスフォーメーション(DX)は、宿泊業界の未来を左右する重要な要素です。
コロナ禍を契機に加速した非対面サービスの導入は、今や標準的なサービスとして定着しつつあります。最新技術を活用することで、限られた人員でも質の高いサービスを提供できる環境が整いつつあるのです。
スマートチェックインで変わるフロント業務の風景
従来、チェックイン手続きには平均15分程度かかっていました。繁忙期には長蛇の列ができ、到着したばかりの宿泊客を疲れさせる要因となっていました。
スマートチェックインシステムの導入により、この状況は劇的に改善されています。専用アプリやキオスク端末を使用することで、宿泊客は数分で手続きを完了できるようになりました。
スマートチェックインによりフロント業務の省力化が実現し、削減された時間をより付加価値の高い接客サービスに充てることができ、結果的に顧客満足度の向上につながっています。
スマートロックと連動したシステムでは、チェックイン手続き後、スマートフォンがそのまま部屋の鍵として機能します。物理的な鍵の受け渡しが不要となり、紛失リスクも軽減されました。
深夜や早朝のチェックイン・チェックアウトにも対応できるため、24時間フロントスタッフを配置する必要がなくなり、人件費の大幅な削減にもつながっています。
AIチャットボットが実現する24時間多言語対応の世界
宿泊客からの問い合わせは、時間を問わず発生します。特に外国人宿泊客の場合、時差の関係で深夜に質問が寄せられることも珍しくありません。
AIチャットボットの導入により、このような問い合わせに24時間365日、即座に対応できる体制が整いました。多言語対応も可能で、英語、中国語、韓国語など主要言語での自動応答が実現しています。
「近くのコンビニはどこですか」「Wi-Fiのパスワードを教えてください」といった定型的な質問から、「明日の天気は?」「おすすめの観光スポットは?」といった情報提供まで、幅広い対応が可能です。
AIチャットボットの活用により、24時間多言語での即時応対が可能となり、フロントスタッフの負担軽減と顧客の安心感向上を両立しています。チャットボットが定型的な問い合わせに対応することで、スタッフは本当に人間の対応が必要な案件に集中でき、きめ細やかなおもてなしが可能になっています。
清掃ロボットや配膳ロボットの導入も進んでいます。これらの技術は、人手に頼らない運営を可能にするだけでなく、非接触サービスを求める顧客ニーズにも応えています。
蓄積されたデータを活用した需要予測や、パーソナライズされたサービス提供も可能になりました。DX化は単なる効率化を超えて、新たな顧客価値の創造につながっているのです。
接客力が顧客満足度を左右する理由

デジタル技術が進化しても、宿泊業の本質は「人によるおもてなし」にあります。どれだけ設備が充実していても、スタッフの対応一つで宿泊体験の印象は大きく変わってしまいます。
しかし現実には、接客レベルのばらつきが大きな課題となっています。同じホテル内でも、スタッフによってサービスの質が異なることが、顧客からのクレームにつながっているのです。
OJT頼りの現場で起きている”教育格差”の実情
多くの宿泊施設では、新人教育をOJT(On the Job Training)に頼っています。先輩スタッフが業務の合間に指導するこの方法は、実践的な反面、大きな問題を抱えています。
教育内容が属人化しやすく、指導する先輩によって教える内容や方法が異なるため、新人スタッフの成長にばらつきが生じます。ある先輩は丁寧に教えるが、別の先輩は「見て覚えろ」というスタンスかもしれません。
標準化されたマニュアルや研修プログラムがない施設では、この問題はさらに深刻です。「何をどう教えるか」が明確でないため、重要な業務知識が抜け落ちたまま現場に出されるケースも少なくありません。
多くの施設では、OJTだけでは教育に限界があることを認識しながらも、体系的な教育プログラムを構築するための時間と人材が確保できないという悩みを抱えています。
結果として、基本的な接客マナーや言葉遣いができていないスタッフが顧客対応をすることになり、「フロントの対応が冷たい」「説明が分かりにくい」といったクレームにつながっています。
スキルのバラつきが招く”人的クレーム”を防ぐには
接客に関するクレームは、施設全体の評価を大きく左右します。設備や立地は変えられませんが、接客は改善可能な要素だからこそ、顧客の期待も高いのです。
スキルのばらつきを解消するには、まず教育体制の見直しが不可欠です。座学研修による基礎知識の習得と、ロールプレイによる実践練習を組み合わせた体系的なプログラムが必要でしょう。
接客マナーや言葉遣いはもちろん、クレーム対応の基本、外国人客への対応方法など、必須スキルを明確にして全スタッフが習得できる仕組みを作ることが重要です。
マニュアル整備も大切ですが、それだけでは不十分です。マニュアルに載らない臨機応変な対応力、いわゆる「ホスピタリティマインド」を育むには、現場での経験共有が欠かせません。
定期的なミーティングでクレーム事例を共有し、どのような対応が適切だったか、どう改善できるかを全員で考える。また、優れた接客事例を共有し表彰する制度を導入することで、スタッフのモチベーション向上とサービスレベルの底上げにつながります。
このような振り返りの場を設けることで、チーム全体のスキル向上が期待できます。
接客力の向上は、即座にリピーター獲得につながります。「あのスタッフがいるから、また来たい」と思ってもらえるような、心に残る接客を目指すことが重要です。
リピーターを増やす鍵は"規模"と"予約経路"にあり
リピーター獲得の成否は、施設の業態や規模、そして予約経路と密接に関係しています。統計データを見ると、意外な事実が浮かび上がってきます。
一般的にホテルの方が旅館よりもリピーター率が高く、小規模施設ほどリピーターを獲得しやすいという傾向があります。この違いを理解することが、効果的なリピーター戦略の第一歩となります。
なぜ旅館よりホテルの方がリピーター率が高いのか
財団法人日本交通公社の調査によると、旅館では宿泊客に占めるリピーター比率が「10%未満」と答えた施設が46.1%に上ります。一方、ホテルでは「10%未満」は15.2%にとどまり、半数以上が「10%以上30%未満」のリピーター比率を持っています。
この差はなぜ生まれるのでしょうか。大きな要因は、利用目的の違いにあります。
ビジネス利用が多い都市型ホテルでは、出張で定期的に訪れるビジネスパーソンが自然とリピーターになります。同じ地域に何度も出張する際、使い慣れたホテルを選ぶのは当然の心理です。
一方、観光目的で利用されることが多い旅館では、「一生に一度の記念旅行」「特別な日のお祝い」といった特別な機会での利用が中心となります。同じ場所に何度も観光に行く人は限られるため、必然的にリピーター率は低くなります。
しかし、これは旅館がリピーター獲得に不向きということではありません。むしろ、一度の滞在で強い印象を残すことができれば、「記念日にはあの旅館に」という形でのリピーターを生み出すことが可能です。
実際、リピーター率の高い旅館に共通するのは、独自の魅力や特別な体験を提供していることです。料理、温泉、接客、すべてにおいて「また来たい」と思わせる何かがあるのです。
出典:財団法人日本交通公社「JTBF宿泊客動向調査」
小規模施設の強みと直接予約がもたらす好循環
興味深いことに、客室数の少ない小規模施設ほどリピーター率が高い傾向があります。これは旅館でもホテルでも共通して見られる現象です。
小規模施設の強みは、スタッフと宿泊客の距離が近いことにあります。顔と名前を覚えてもらいやすく、個々の好みに応じたきめ細やかなサービスが可能です。
「いつものお部屋をご用意しました」「前回お気に召していただいたワインを今回もご用意しています」といった、パーソナルな対応が自然にできるのが小規模施設の利点です。
大規模ホテルでは、どうしてもサービスが画一的になりがちです。効率を重視するあまり、個々の顧客との関係構築がおろそかになることもあります。
予約経路もリピーター率に大きく影響します。リピーター率の高い施設ほど、OTA(オンライン旅行代理店)経由の予約が少なく、直接予約の比率が高いという明確な傾向があります。
これは、リピーター客が施設の公式サイトから直接予約することで、会員特典や割引を受けられるためです。施設側も、手数料のかからない直接予約を促進するため、さまざまな優遇策を用意しています。
初回はOTA経由で予約した客も、チェックアウト時に次回使える割引券を渡したり、会員登録を促したりすることで、2回目以降は直接予約に誘導できます。
この好循環を作り出すことが、リピーター獲得の重要なポイントです。小規模施設の強みを活かしたパーソナルなサービスと、直接予約への誘導を組み合わせることで、効果的なリピーター戦略が実現できるのです。
リピーター獲得がもたらす経営へのインパクト

リピーター獲得は単なる理想論ではありません。具体的な数字で見ると、その経済的効果は驚くべきものがあります。
マーケティングコストの削減、安定した収益基盤の構築、そして口コミによる新規顧客獲得。リピーター戦略がもたらす好循環は、宿泊施設の経営を根本から変える可能性を秘めています。
新規顧客の5倍!知っておきたいコスト差の真実
マーケティングの世界では「1:5の法則」という言葉があります。新規顧客を獲得するコストは、既存顧客を維持するコストの5倍かかるという法則です。
宿泊業界でこの差を具体的に見てみましょう。新規顧客獲得には、広告出稿費、OTAへの手数料、キャンペーン費用、そして集客に関わるスタッフの人件費などが必要です。
仮に一人の新規顧客を獲得するのに1万円のコストがかかるとすれば、リピーター獲得にかかるコストは2,000円程度で済む計算になります。
既存顧客へのアプローチは、メールマガジンやDM、会員限定特典の提供など、比較的低コストで実施できます。すでに施設を知っている顧客への訴求は、ゼロから信頼関係を築く必要がないため、効率的なのです。
さらに重要なのは、リピーターがもたらす収益の安定性です。閑散期や平日の稼働率向上に、リピーターの存在は大きく貢献します。
「いつものホテルだから」という理由で、多少高くても、時期が悪くても利用してくれるリピーター。彼らは価格競争に巻き込まれにくい、貴重な顧客層なのです。
Bain & Companyの調査では、顧客リテンション率を5%向上させるだけで、利益率が25%以上も向上するという驚きの結果が報告されています。
リピーターは滞在中の消費額も高い傾向があります。施設への信頼があるため、レストランや付帯サービスの利用率が高く、客単価の向上に貢献します。
出典:Bain & Company「Prescription for Cutting Costs: Loyal Relationships」
口コミが生み出す”無料の宣伝効果”を最大化する方法
リピーターの価値は、直接的な売上貢献だけではありません。彼らが発信する口コミは、最も信頼性の高い宣伝となります。
満足したリピーターは、自分の体験を家族や友人に積極的に話します。SNSでの投稿、口コミサイトへの書き込み、そして何より、直接的な推薦。これらはすべて無料の宣伝活動です。
口コミ効果を最大化するには、まず「語りたくなる体験」を提供することが重要です。期待を上回るサービス、印象的な出来事、心温まるエピソード。これらが口コミの種となります。
次に、口コミを促す仕組みづくりも大切です。チェックアウト時に「ご感想をお聞かせください」と声をかける、SNSでの投稿を促すハッシュタグを用意する、口コミ投稿への特典を設けるなど、さまざまな方法があります。
重要なのは、ネガティブな口コミへの対応です。不満を持った顧客の声に真摯に対応し、改善への取り組みを示すことで、むしろ信頼を高めることができます。
リピーターからの紹介で来た新規顧客は、最初から施設への期待値が高く、リピーター化しやすいという好循環も生まれます。一人のリピーターが、新たなリピーターを生む。この連鎖反応こそが、持続可能な経営の鍵となるのです。